
第1話 オフィス「風の予感」 =1=
|
運命は時に、なんの前触れもなく、新たな展開をみせる。 僕の場合それは、ひとりの女性との出会いだった。 彼女は春の太陽だった。 夏の照りつける太陽ではない。あくまで春の太陽だ。春からイメージさせる優しさをも含んだ照射だった。 ゆっくり訪れる夜明けのように彼女はそっと僕に寄り添い、僕の生き様を揺さぶった。 |
|
僕は大学に籍を置くフリーターだ。 それはフリーターじゃなくて、大学生だって? そりゃまあ、学生だって言ったほうが世間体はいい。けど、そこまで僕の面の皮は厚くない。 だって、事実上大学に通ってないのだし、バイト三昧の生活を続けているんだから。 学費も生活費も仕送りは受けていない。全てバイトで賄っている。 だから、金銭面では親に対する罪悪感はないけれど、それはあくまでお金についてだけの話だ。一応親としては4年で卒業してそこそこのところに就職して、みたいな期待はあるはずで、僕が実際、今どうなっているのかを親に説明するのは気が引けた。 だから親には内緒である。 大学には休学届けを出してある。 なあに、いざとなったら「就職が決まらなかったので、わざと卒論を提出せずに、留年した。就職浪人なんてカッコワルイから」とか、「最終学年で油断して留年してしまった」とか、適当な言い訳はいくつか考えてある。大丈夫だ。 もっとも、来年、復学できればの話である。 さすがに2年連続で休学することになってしまったら、もっと別の言い訳が必要であろう。 ともあれ、そんなわけで僕はフリーターなのである。 そして、今日はバイトがない。今日の僕は時間に束縛されない。僕は昨夜から読み続けている本を、夜が明けてもそのまま読み続けていた。 シリーズものの文庫を古書店で一挙に7冊も買ったんだから仕方ない。一般書店でなら1冊ずつ順番に買えばいいんだけれど、古書店の場合、売れてしまったら次の入荷の保証はない。だから、欲しいものは見つけた時に買うのがコツである。そして、買ってしまった限りは、最後まで読んでしまいたいのが人情というものだ。 バイトのある日なら、夕方からの出勤に備えて一眠りし、目覚めた後は、掃除はしないけれども洗濯をするとか銭湯に行くなんかの用事はある。しかし、今日はフリーである。眠くなるまで本を読み続け、眠くなったら寝る。それでいい。 とはいえ、散らかり放題の部屋の中に朝日が差し込んでくると、さすがに寝転がったまま時々姿勢を変えつつ、本だけ読んでいるというのは不健康に思えた。というより、飽きてしまったのである。 ちょっと、でかけるか。 太陽光線の中に埃がキラキラと輝きながら舞い踊るさまが目に入るのも、精神衛生上良くない。お腹もすいたが冷蔵庫には何も無い。喉も渇いた。 水道の蛇口に口をつけ、生水を喉の奥に流し込んで再びふとんに横になる、というのもこれまた一興ではあるけれど、さすがにそこまで自堕落にはなりたくない。万年床だし、部屋は散らかりまくっているけれど、生水で飢えと乾きを癒してまでも外出を拒否するほどに面倒くさがりになってしまっては、いくらなんでも、もう終りだろう。 せめて飲食物はきちんととろう。それが僕の中に残された、最後の美学である。 4冊目の文庫の最後の10ページを、乾ききった口の中に唾液を補充しつつ急いで読み終えた僕は、5冊目の文庫をジーンズの尻ポケットに突っ込み、財布を手にしてアパートを出た。 そしてコンビニに駆け込む。 鮭マヨネーズおにぎりと、ハムたまごサンド、そして缶コーヒーを2本。 これでどこが美学かと思うけれど、バイト生活で裕福じゃないから、美学を語れるような朝食なんぞとれやしない。もっとも、それを言うなら自炊の方が安くつくんだけどね。 だけど自炊は面倒くさい。僕は面倒くさがり屋なのである。ん? なんだか矛盾しているな。 そして、僕は公園に向かった。 決して広い公園ではないが、僕のお気に入りの場所だ。木々が茂り、その下にいくつかのベンチがある。すぐ側を幹線道路が走っていて環境がいいとは言えないが、それなりに市民の憩いの場になっている。 早朝から散歩する老人や犬を連れた人たち。小さな子供の手をひいた若いお母さん。所在なげにベンチに座る人。……ここは中国ではなく、あきらかに日本なのだが、太極拳みたいなことをやっている人もいるし、全身汗まみれになって中年太りの腹をTシャツ越しに思いっきり透けさせているおじさんもいる。そして、通勤の途中で足を止め、灰皿の傍であわててタバコをふかし、あっという間に立ち去るサラリーマン。そんな人からしたら、のんびりとおにぎりを口に運び、缶コーヒーを飲んでいる僕の姿は、どう見えるのだろう。「羨ましい」だろうか。それとも、「へ、人生の負け組め」だろうか。まさか「恨めしい」じゃないだろうな。 10分ほどそういう光景を眺めていたら、おにぎりもサンドイッチもなくなってしまった。僕は2本目の缶コーヒーを開けて一口すすり、それから本を読み始めた。 |
|
「すいません、ここ、いいですか?」 女性の声がした。若い声だ。僕は活字を追いながら「どうぞ」と言った。 隣に座ったらしい若い女性に僕は全く興味が無く、いつしか忘れていた。読書をはじめると没頭するタイプなのだ。 ひとつの章を読み終えたとき、隣に人の気配を感じた。 ひとつの章といっても、シリーズもの全7巻の5巻目。1冊ごとにひとつのストーリーは完結しているとはいえ、物語り全体を通しての流れもある。その全体の流れは、伏線らしきものをちらつかせながら、しかしちっとも進行せずに5巻の物語へと突入していく。 巻ごとの個別の物語はもういいから、肝心のかつ待つはどうなるのか教えてくれ。 ちょっと焦れったくなってくるが、いつしか5巻の物語に引き込まれてゆく。 隣に感じた人の気配は、もしかしたら「すいません、ここ、いいですか?」と声をかけてきた彼女だろうか。きっとそうだ。あれ以来、人による空気の揺らぎを感じなかった。 もちろん、風も吹けば木々の枝葉も揺れる。 しかし、人による空気の揺らぎというのは、そういう自然のものとは異質である。彼女はあれから、ずっといたのだろうか? ふと横を見る。おそらくまだ10代後半の少女だろう。苦しそうにハアハアと言っている。彼女が隣に座ってから相応の時間がたっているのに、まだ息が整っていないとみえる。これはもしかしたらただ事ではないかもしれない。 そして、流血。 ぼくはびっくりして「どうしたの?」と、小さく叫んだ。 「ゲゲッ」とかなんとか大声で驚愕、なんてオーバーアクションをとりそうになったが、どうもオオゴトにしてはいけないような雰囲気を感じたのだ。 前頭部が割れているのだろうか。前髪で出血場所が不明確だが、額から唇の横へ血が伝っている。血はすっかり乾いてこびりついていた。 「どうしたの? 何があったの? 大丈夫?」 苦痛をこらえて無理に笑顔を作りながら、彼女は「交通事故に遭っちゃいました」と、言った。 交通事故に遭っちゃいました、じゃねえ。 交通事故? オオゴトじゃないか。公園のベンチにのんびり座っている場合ではない。 「病院……」 行ったの? などと、聞くまでもない。見るからに怪我をしてそのままだ。 「きゅ、救急車……てほどじゃ、ないよな……」 「大丈夫です。頭をちょっと打っただけだから。しばらくこうしてれば」 「大丈夫なもんか」 「いえ、大丈夫です。病院とか、警察とか、まずいんです、ホントに。赤信号なのはわかってたんですけど、ボーっとしてて前に出すぎて……、目の前を大型車が通り過ぎて、びっくりして。そのせいで転んで、地面で頭を打っただけですから。痛みが収まれば、顔を洗って帰ります」 それは厳密には交通事故ではない。車にびっくりして、自分でコケただけだ。 まったく、脅かさないでくれよ。そう思ったけれど、口には出さなかった。 |
|
僕はアパートで一人暮らしだったので、彼女を連れて帰った。 万年床だし、その周囲の散らかり具合とその内容については色々とまずいものもあるのだが、幸い食卓の上は綺麗に片付けてあった。僕にとってダイニングテーブルは、ご飯を食べるだけの場所じゃない。新聞だって読むし、ノートパソコンだって開く。便利生活のためには食卓は片付けておくべきなのである。 もちろん、万年床も、その周囲が散らかっているのも、便利生活のためである。寝床に横になったまま、必要なものにはたいてい手が届くように配置してある。 それも、考えに考え抜いた頭でっかちの配置ではない。日々の暮らしの中で、自然とそういう配置に落ち着いたという、いたって現場主義的な経過と結果である。 さて、傷口の方はというと、確かにたいしたことないようだ。彼女はもう痛みに顔をしかめることもなくなった。傷そのものより、ショックの方が大きかったのかもしれない。 シャワーを浴びたいという彼女を、また傷口が開くといけないからと制し、洗面所で顔を洗うようにと新しいタオルを渡す。お湯が使えるように、湯沸かし器のスイッチを入れてあげた。 僕はパジャマを彼女に貸した。破れたり血が付いたりしている服を「ごめんなさい。捨てていいですか?」と言ってから、彼女はゴミ箱に入れた。 コーヒーをいれて一緒に飲む。 僕の向かい側に座って、カップを抱きしめるようにして少しずつコーヒーを飲む彼女は、まばゆいほどに美しかった。どこがどうというわけじゃない。存在そのものがまばゆいのだ。 左右が少しアンバランスだけどパッチリとした特徴的な瞳、小さすぎる鼻、笑うとふくらむ頬、形はいいけれど少し薄い唇。綺麗に毛先を揃えたはずなのに、そのまま放置して4〜5センチほど伸びた、という感じの横着ボブ。 それぞれ欠点を含みながらも、全体としては美しく、可愛い。 それにしても、何だって見知らぬ女の子が僕の部屋でくつろぎ、お茶なんか飲んでいるんだろう? もちろん僕が招いたからだが、ここに彼女がいることが、とても不思議に思えた。 本も公園も缶コーヒーも交通事故も何もなかったかのように、ちょんまりと彼女はこの部屋にマッチしていた。 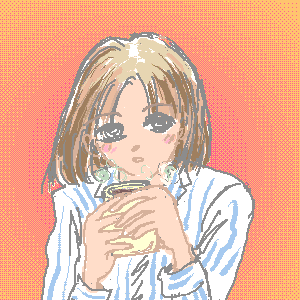 「ところで、君は誰?」 「ところで、君は誰?」僕は訊いた。 訊いてから、あれ? と思った。そんなことを知って、どうしようというのだろう? 気分がやわらいだら、きっと彼女はここを出て行く。出て行ってもらわないと、僕も困る。いや、別にこの子だったらいてくれてもいいんだけれど、お互いそういうわけにはいかないだろう。だったら、彼女の素性を知ったところで詮無いことだ。 まあ、無言というのも気詰まりだから、単なる無駄話。そういうことにしておこう。 言いたくなければ、言わなければいい。 横着ボブの彼女は、大事そうに抱えていたセカンドバックから、名刺入れを取りだした。 「んっと、これでいいかな?」 名刺入れから一枚引き抜いた紙片を差し出す。ビジネスシーンに馴染んだOLのように慣れた所作だった。バイト先の研修で、名刺の渡し方、受け取り方なんていうのをやったことがあるから、僕でもそれくらいはわかる。もっとも所詮はバイト、そんな研修は役に立たなかったし、そもそも名刺なんか作ってもらえなかった。サークルや学生会などに所属してる学生は名刺を持ってたりもするようだけれど、僕には縁がない。 僕は名刺を受け取る前に、もう一度彼女を見た。10代後半、その印象は変わらなかったが、顔を洗って血糊を落とした彼女はさらに若く見えた。女子高生と言っても通じるだろう。けれど、ちょっとおすまし顔でよどみなく名刺を差し出す彼女は、年上のようにも感じさせた。 名刺には、「(有)オフィス風の予感 主任調査員 立華清花」と記されていた。 「たちばな……?」 「たちばな、さやか、と読みます。」 「たちばな、さやか、さん」 「はい」 彼女は堂々と、そして爽やかに微笑んだ。名は体を表すというが、まさしくその通りだった。清い花が、すっと立ち上がった感じ。しかも優美で華がある。 オフィス風の予感、という会社名も爽やかだ。けれど、その社名にそぐわない肩書きだなと思った。 調査員……。 興信所、保険支払いの査定、スパイ、密入国者などなど……。なんかうさんくさいものばかり連想してしまう。 いったい何を調査する会社なのだろう。 そして、この若さで「主任」とは。既にそれなりの功績があるとか、あるいは特殊技術を持っているとか、そんなところか。侮れないと思った。 「不躾なんですけが、『オフィス風の予感』って、何をしてる会社なんですか? そして、差し支えなかったら、年齢も教えてくれると嬉しいんですが」と、僕は言った。 なんだか喋り方が変だ。 不自然な丁寧さを含んだ台詞になってしまっている。きちんとした職を持っていること、そして肩書きまであること。さらに、堂々とした名刺の出し方。これらに気おされたらしい。 もっともパジャマを着ているところが少々ちぐはぐだけど。 立華清花はうふふっと笑った。 「年齢ですか。じゃあ、プライベートモードで喋りましょ。少なくともあなたよりも年下だと思うから、中途半端に丁寧な言葉遣いはやめてくれると嬉しいな。わたしも、生意気かも知れないけど、できればタメ口で話したいし。ですます調で喋っていると、仕事じゃないのに、仕事みたいな感じがして好きじゃないの。いい、かな?」 いいかどうか返事を待たずにもうタメ口になっている。彼女の切り替えの早さは、頭の回転の速さによるものか。それとも僕がついていけてないだけなのか。 いずれにしても、自然に口をついた彼女に対する「ですます調」をやめるには、少し努力がいるようだった。 「はい、いいですよ……、じゃなくて、ああ、いいよ、かな?」 「うんうん。わたしもそのほうが気楽でいいや」 立華清花はざっくばらんに笑った。無邪気さをめいっぱい含んだ笑顔。僕までほのぼのした気持ちにさせられる。 「で、仕事の方なんだけど、これはちょっと一言で説明するのは難しいな」 「でも、何かを調査する仕事なんだろ?」 よし、タメ口っぽく言えた。この調子だ。 「そうそう。調査する仕事」 「だから、それは、何を?」 「国家機密」だなんていわれたらどうしようかと思ったが、それは杞憂だった。しかし、考え方によっては、それは国家機密よりも遥かにやっかいなものだったかもしれない。 「人の、心。かな?」と、清花は言った。 「ふうん」とは言ったものの、なんだかよくわからない。 僕はコーヒーをすすろうとして、カップの中が空っぽになっていることに気がついた。 「おかわりする? インスタントのようだし、それならわたしでも入れてあげられるよ」 清花も話題を変えたかったのか、僕のカップを手にして、さっさと立ち上がる。 「じゃあ、頼むよ」 それにしても、なんなんだろうね、このシチュエイション。今日初めて部屋にやってきた結構イケてる女の子に、僕はコーヒーを入れてもらっている。ま、いいか。 彼女はキッチンに立ちながら、つまり僕に背中を向けながら、「ねえ、あなたは……なんて呼べばいい? 自己紹介してよ」と言った。 「名前は橘和宣。偶然だけど、同じ『たちばな』。でも、漢字は違うよ。一文字の方。21歳。学籍だけ大学に置くフリーダーだよ」 「学籍だけ大学に置くフリーター?」 わざわざ復唱してから、一拍の空白を置いて、けらけらと彼女は笑った。なんとなく僕の状況を察したようで、それ以上は訊いてこない。 「苗字が同じなのね」 「そうだね。偶然だね」 「なら、下の名前で呼んでいい?」 「いいよ」 「じゃあ、和宣君、ううん、ええと、呼び捨ての方がしっくりくるかな、和宣、うう〜ん。」 彼女は何度か、カズノリくん、カズノリ、かずのりクン、かずのり、とつぶやいた。 「やっぱ、呼び捨てでいいかな?」 下の名前で呼ばれることにも呼び捨てにされることにも違和感を感じた。これまで小中高と過ごしてきた中でも、僕はファーストネーム呼び捨て、という経験が無い。周囲にはいたが、恋人でもないのに、そんな間柄の男女を見るたび、羨ましいような、こそばいような、そんな気分にさせられてきた。 いずれにしても、僕と彼女がどう呼びあうことになろうと、それはたいしたことじゃない。自己紹介を終えてコーヒーを飲み干したら、僕たちは多分それっきりだ。通りすがりの出会いと別れ。短い時間を狭い部屋で共有しただけの仲。 「どっちでもいいよ」 「じゃあ、節約モードで、和宣。わたしのことも清花って呼んでくれたらいい」 「そうするよ」 「で、何の話だっけ?」と、清花は視線を斜め上に向けた。「そうそう。わたしの会社の仕事だったよね。それはそうと、和宣はこれから暇? フリーターの人って、イメージ的には暇そうなんだけど、結構バイトで忙しかったりするのよね。でも、もし暇だったらわたしの仕事に付き合ってくれない? 助手、っていうのかな、ちょっと手伝ってくれると助かるんだ。そうすれば、どんな仕事かもわかるわよ。もちろん、バイト代は払うから」 「偶然にも、このあと僕は暇なんだ」と、僕は答えた。もちろん、自ら望んで暇なわけじゃない。貧乏なのである。貧乏だからバイトのない日は用事を入れない。余計な出費を避けるためだ。 家賃も払わないといけないし、学費も納めなくてはならない。生活費だってかかる。学生のくせにフリーターなのは、「仕送りが無いから小遣い稼ぎ程度のバイトでは生活できない」ためである。 |
|
実際、授業に出ながら、バイトで稼ぐ、というのはたやすくは無かった。 考えてみたら、当然だ。「学生」「社会人」という区別があるくらいなんだから、どちらか一方だけをしている、というのが普通である。その両方をこなすんだから、時間的にも、体力的にも、精神的にもキツくて当たり前なのである。何かを犠牲にしなくてはいけないから、生活だってメチャクチャになる。 入学金と一年の前期授業料は親に借りたが、入学したらさっそく後期授業料をためなくてはいけない。1年間はなんとかなったけれど、それも前期の授業料を親に前借りしたからだ。 必死になって勉強もバイトもして、後期の授業料はためた。でも、そこでぷっつりと緊張の糸が切れてしまった。バイト疲れが蓄積して、授業料は払ったというのに、肝心の授業に出る気力が失われたのだ。 このままでは単位を落としかねない。バイトを休んで集中的に勉強することにした。しかし、いざ下宿にいる時間が長くなると、これといった成果があがらないままダラダラと過ごしてしまう結果になった。遊びの誘いにもついつい応じてしまう。 かろうじて留年はせずに済んだが、2年生の前期授業料も親に借りることになった。前借することになり、後期授業料は自分でなんとかしたものの、後半は前年と同じ経過を辿り……。 さすがに3年連続で前期授業料を親に前借するのは気が引けた。言い出せなかった。 そこで僕は、休学して資金稼ぎに専念することにした。 休学中は学校に納める費用は10分の1で済む。その程度の費用は2年生の後期に稼いでいた。 そして、休学して3ヶ月。いくつかのバイトを掛け持ちしたり、単発のバイトを繰り返したりした。収入は確かに増えたが、支出はさほど減らない。外食にしても、コンビニにしても、学内に比べたら物価が高いからだ。 DVDを借りたり、本を買ったりも増えた。学校へ行って、友達とバカ話をすることがなくなった分、娯楽を必要としたからだ。収入が増えた分、まあいいかと自分に甘くもなった。 定期券はいらなくなったけれど、これまでは定期の範囲内で用を済ますことが多く、プラスアルファの交通費はほとんど使わなかった。しかし今はその都度払わねばならない。これがバカにならない。レギュラーのバイト先でも定期を必要とするほどではなく、回数券ではいかほども安くならない。 そんなわけで、清花が僕の目の前にぶら下げたバイト料は魅力である。徹夜明けでキツイといえばキツイけれど、寝転がって本を読んでいただけだし、生活がキツイ方が辛い。 自分より年下の女の子に「バイト代払うから、手伝ってよ」と言われるのはシャクだけど、プライドよりも現実だ。 「わかった。やるよ」 「ありがとう。助かるわ」 清花は、ありがとう、と語尾を上げ、助かるわ、と語尾を下げた。 「じゃあ、バイト代ね」 清花は名刺を取りだしたときと同じように、セカンドバックからお金を引っ張り出した。銀行の帯封がかかった一万円札の束。帯封があるということは、単位は100万円? そんなものを彼女は持ち歩いているのか。 帯は少し緩んでいる。既に何枚かを抜き取った後のようだ。それでも90万円前後はあるだろう。 「そうね、とりあえず5日分の日当ということで、5万円」 いち、にい、さん、し、ご。5枚を数えて僕に手渡す。当たり前のように僕の目の前に差し出すものだから、僕も自然に受け取ってしまった。 受け取ってから、焦った。 「こんなに?」 「多くはないわよ。日当計算だから。時給じゃないから残業もつかないし、いつ始まっていつ終わるかわからない。あ、必要経費は別に出すからね。わたしと一緒に行動するときはわたしが払うけど、単独行動の時は立て替えといてね。領収書、忘れちゃダメよ。そうそう、日当の領収書も書いてもらわなきゃ。はんことか持ってる?」 はんこは持っているけれど、何だか一日一万円で買われたような気がした。まあ、労働者というのは、もともとそういうものなのだろう。 「あ、でも、今日は暇だけど、明日はバイトが入ってる。5日間は、ちょっと……」 「時間は調整してあげる。でも、バイトの方も調整してね」 「え、ああ、うん」 いや、それよりバイトを断ろうか。 不意に抜ける学生バイトの穴を僕はこれまでずっと埋めてきた。なにしろ、一日中、時間はあるのだ。だからこそ重宝がられてきたのだけれど、たまには風邪をひくのも悪くない。 「じゃあ、行きましょ」 清花が普通より少しだけ高いトーンの声色で宣言した。 ところで彼女の年齢だが、「少なくともあなたよりも年下だと思う」でごまかされて、結局、知ることはできないままである。 |
|
パジャマで外出するわけにはいかないので、僕はジャージの上下を清花に貸した。最初からそうすればよかったんだ。なぜ僕はパジャマなんか彼女に手渡したんだろう? そうだ、その間に洗濯をすればいいやと思っていたのだ。まさか「捨てていい?」なんてことになるとは思っていなかった。 あっさりものを捨てる感覚といい、セカンドバックに札束を放り込んで持ち歩くことといい、僕の理解の中にはない。彼女と僕では、金の流れ方が違うのかもしれない。と思いきや、「服、買わなくちゃね」と彼女が入って行ったのは、ディスカウントのジーンズショップだった。ブランドやメーカーへのこだわりはないようだ。 清花はGパンとTシャツを買い、その場で着替えた。 オーソドックスなストレートジーンズと、何の変哲も無い白のTシャツ。胸元が深めのVカットになっているが、女性物としては珍しくも無い。街を普通に行動するのには差し支えなかろう。とはいうものの、おしゃれからは縁遠いように思えた。 試着コーナーのカーテンから顔だけ覗かせて、「すいません、これ、このまま着て帰ります」と言うと、店員はニッコリと頷いた。たたみ直して袋に入れるなどの手間が省けるから、店員はちょっと嬉しかったのかもしれない。 駅の時計は間もなく11時になろうとしている。 「ちょっと待ってて。預けてある荷物、とってくる」 コインロッカーから清花はスポーツバックを取り出し、ファスナーを開けた。中から綺麗にたたんだジャケットを持ち上げる。裾が短いのでビジネス用というよりもカジュアルなものだが、それでもジャケットを羽織るだけで彼女は見違えた。 ジーンズにTシャツだというのに、それなりにきちんとした格好に見えるからたいしたものだ。それに比べて僕は、どことなくくたびれたGパン、よれたポロシャツ、そして、どんなに手入れしても消えそうに無い皺が刻まれたウインドブレーカー。幸いスニーカーに目立つ汚れはないものの、仕事に行く、というスタイルじゃない。 僕がそのことを告げると、清花は「いいのいいの。大学生のバイトなんだから、そんなものよ」と、気にもしていない様子だ。 コインロッカーから切符売場へ移動する。さくさくと歩く清花。足取りは別段速いわけではないのに、なぜか後を追う僕との距離は開いてしまう。駅を往来する様々な人々に行く手を遮られて、僕は思うように進めない。が、清花の前にはそういった障害物が現れない。まるで彼女の行く手をまわりの皆が協力して開けてくれているようですらある。 もちろんそんなことはありえない。彼女はごく自然に周囲の状況を読み、常にベストのルートを選択しているのだ。真似できない。 僕が清花に追いつく頃には、彼女は2枚の切符を買い終えていた。 そのうち1枚を手渡され、「下り電車だから」と、僕は促されるまま改札口を通り抜けた。 電車に乗って、入り口の脇に2人ならんで立つ。混雑はしていないが、空席があるほどじゃない。 「とりあえず、これ、読んどいて」 清花はセカンドバックの中からたたんだ紙切れを取りだした。全く、何から何まで入ってるんだよな。そのセカンドバック。天気が良く、のんびりとした陽射しが窓越しに僕の手元に届く。 広げた紙切れはA4サイズで何枚かが綴じてあり、1番上の紙には調査依頼書と書いてあった。 まず依頼人の住所氏名電話番号などのプロフィールが記されている。依頼内容は、次のようになっていた。 調査対象人物:山本ふね(84)女性 死因:老衰 備考欄には、山本ふねのプロフィール他、簡単な個人情報が書かれている。 調査依頼内容は、「後継者が無いまま残されたお好み焼き屋について、祖母はどう考えていたのか。それで構わないと思っていたのか、それとも、誰かに跡をついで欲しいと切望していたのか」であり、特記事項として「なお、このお好み焼き屋は山本ふねの死後、息子の手によって不動産業者に売却を依頼されており、最近買い手が見つかった」と付け加えてある。 待て。調査対象人物は既に死亡しているってことか? そんな僕の気持ちに気付いたのかどうか、タイミングよく清花が言う。 「簡単に説明するわ。オフィス風の予感は、死者の気持ちを調査する会社。故人がどんな気持ちで死んでいったか。それを調べて遺族に報告するの」 「じゃあ、これは」と、僕はA4の調査依頼書をわずかに持ち上げる。 「和宣に渡したのは、山本さんのお孫さんからの依頼。息子さん、つまり依頼人のお父さんは宝石商でね。自分でお店を持っているからお好み焼き屋を継ぐことはできないし、お孫さんご本人はサラリーマン。会社を辞めてお好み焼き屋を継ぐかどうか悩んだ末、おばあちゃんの気持ちを知りたい、とこうなったわけね。『このまま売ってしまってもいいんだろうか』って、ちょっと感傷的にもなってるみたい。会社勤めが肌に合わないみたいな印象も受けたわ。上手い具合に理屈がつけば、会社をやめるのを正当化できるかもってな節も感じられたかな。もっとも、お好み焼き屋はもう3年も営業していないから、いまさら再開させたところで常連さんが戻ってくるかどうかもわからない。つまり経営できるかどうかはわからないわけよ」 「ふ〜ん、なるほど」 なるほどなんて言ってみたものの、疑問が残った。正直、僕にとって「そんなこと調べて何になる?」だ。 そもそも買い手が見つかったのなら、手遅れじゃないのか? いや、書面なんかで、いわゆる契約行為をしていなければ、まだ間に合うのかな? しかし、死ぬ間際にあれやこれやと思い悩むのならわかるけれど、今となっては、するもしないも本人の一存のはずだ。いまさら死者の気持ちがどうこうという問題ではなかろう。 感じたままを述べると、清花は「大切なのは、死者の気持ちじゃなくて、それを知りたいという遺族の気持ち。これがわたしたちの仕事なのよ」と言った。 「う〜」 唸ってしまった。死者の気持ちを調査する、と言いながら、大切なのは死者ではなくて生者の気持ち。 「でも、こんなの、どうやって調べれば」 呟く僕。なにしろ本人は死んでいる。 「この案件はわたし達が抱える仕事の中では簡単な方だわ」と、清花はこともなげに言う。「親しかった人を探して、晩年の山本さんが普段どんなことを言ったり行動したりしたかを調査すればいいのよ」 「それだけでわかる? よほどあちこち訊きまくらないと無理なんじゃない? そうしたところで、必ず情報が得られるという保証もないよね。そもそも本人に確認することができないんだから」 「もう。始める前から弱気になってどうすんのよ」 清花は頬を膨らませた。 「もうこれは『風の予感』が引き受けた仕事なの。それに、和宣だって、このバイト、やるって言ったわ」 「そりゃ、そうだけど」 「それにね、詳しく調査すればいいってもんでもないのよ。報告書に書くレポートに矛盾がない程度の証言や証拠が得られればそれでいいの」 「な、なんだよ、それ」 僕はムッとした。 後で考えると、清花は「難しく考えすぎないで」とか、「仕事にはコツがあるのよ」とか、そういうことを言いたかったのではないかと思う。でも、そのときの僕には、「適当に話をきいて、うまいことまとめればそれでいいのよ」と聞こえた。 僕が熱くなる必要などないのだけれど、いかなる調査結果であっても死者は「ちょっとまって、それは違うよ」と口を挟むことはできないんだから、とりあえず矛盾がなければいいなんていうのは違うと感じたのだ。 僕は思わず、「それって、辻褄をあわせればいいってこと?」と言い返していた。 「そうは言ってないわよ」 「けど、なんだか遺族の人が納得したら、それでいいんだって聞こえたけど……」 声を荒げたわけではない。これまでと同じ調子で喋っている。でも、気持ちには波が立っていた。 「だから、そうは言ってないって。でも、依頼人が納得しなくちゃいけないっていうのは、正解。ま、一度やってみればわかるわよ」 清花はポンと僕の肩を叩いた。 「少なくとも安心したわ。和宣がマジになってくれて。『な〜んだ、そんなことでいいの』なんて言われたら、逆にどうしようかって思ってたかもね」 別にマジになったわけじゃない……なったのかな? 「変死体なら警察が遺体を解剖して調べてくれる。死因が病気なら医者が教えてくれる。だけど、どんな気持ちで死んでいったかなんて、誰も調べてくれない。本当はそれが1番大切なのにね」と、清花は付け加えた。 僕は返事できなかった。 「でね、わたしはもうひとつややこしいの抱えているから、できれば全面的に任せたいんだけど」 任せるって、おいおい……。こんなド素人にか? とはいえ、仕事そのものはもう断れない。ギャラを受け取ってしまっている。いや、お金を突っ返せば断れるんだろうけれど、そんな気にはならなかった。 確かに僕は、「調査」ということについてはド素人だろう。けど、人の気持ちは大切にしたい。この想いは、清花にだって負けないと思った。いつのまにか「この仕事、ちゃんとやらなくちゃ」と決心している自分がいる。それを感じたからこそ、清花は僕のようなド素人に「任せる」と言ったのかも知れない。 「お願いね」と、静かに微笑む清花。 のせられたかなとも思ったが、そんなことはどうでもいい。もう、やるしかない。手間はかかるだろう。でも、ひとつひとつの手順は難しくないだろう。ともかく、手を抜かずに丁寧にやろうと思った。 とはいえ、締切はあるだろう。それは守らなくてはならない。 「締切とかあるの? 5日分の日当をもらったっていうことは、そのくらいで完了してくれってこと?」と、僕は質問した。 「ナイス! その通りよ」と、清花は明るく答える。さっきまで、半ばもめかけていたことなどどこへやらだ。 「と、言いたいところだけど、3日もあればできるはずよ」 清花は携帯電話の画面にカレンダーを呼び出した。 「依頼人は7日後に海外出張を控えてるの」と、清花はカレンダーの7日先の日付を指差した。 「遅くとも出発前日には調査報告する約束だから、5日間調査に費やしたら徹夜でレポートを書いて翌日渡す、なんて羽目になるわ。それに和宣は新人だから、早めにわたしに提出してチェックを受けて欲しいの。そのあとで社長のチェックが入るわ。となると、やっぱり今日を含めて3日間てとこかしら」 今度は3日後の日付を指先で示す。 「4日目には提出して頂戴。それなら不備があってもフォローがきくし」 「うん、わかった」 「それから、別行動した部分については、毎日報告すること。オッケー?」 「ああ、オッケーだよ」 「あと、ひとつ忠告ね。繰り返しになるようだけど、この仕事は、死人のためにやってるのではなくて、依頼人、つまり生きてる人のためにやってるんだからね。そこんとこ、忘れないで。じゃあ、この件は任せるから」 「ん。了解」 そう返事して、僕は自分の気持ちを整理した。 死人の気持ちを調査する。そんなことが商売になることに若干の後ろめたさを感じないでもないが、要するに本人が死んでしまっている以上これが正解だなんてことは誰にもわからない。誰にもわからないことを何とか調べる。そして生きている人のために報告する。 ……それはそれで意義深い仕事なのだろう。 少なくとも、マニュアルに忠実に作り笑いを浮かべながらファーストフードの販売をしたり、コンピューターのディスプレイを終日相手にしたり、あるいは工場のラインで単純作業を繰り返したり、そんなバイトに比べて、遙かに人間くさく、人の役に立ち、やりがいがあるような気はする。 「やれるだけ、やってみるよ」 「うん、助かるわ。よろしく頼むね。困ったことやわからないことがあったら、いつでも携帯に電話して」 「そうする」 清花は僕の目を見つめ、それから大きく息を吐いて、窓の外に目をやった。 「もうひとつの案件、仕上げの証拠固め、みたいなところまで進んではいるんだけど、てこずっちゃって。どうしてももう1人、欲しかったのよね。本当にありがとね」 そう言ったきり、窓の外から視線を戻そうとはしなかった。 それは、風景を楽しんでいるようでもあったし、会話を打ち切って考え事をしたいからわざとそうしているようでもあった。 |
